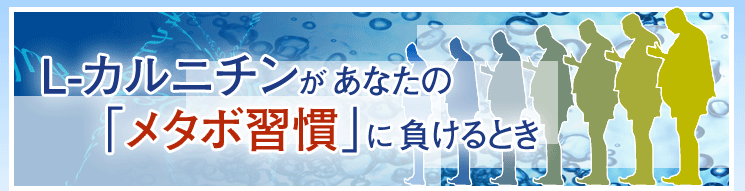HOME / L-カルニチンとは / L-カルニチン活用術
L-カルニチンとは
L-Carnitine Overview
L-カルニチン活用術
生活習慣病ケア
Lifestyle disease care
L-カルニチンは、「脂肪と直接結合し、脂肪をエネルギーに変える過程をサポートする」他の栄養素には代替できない役割をもつことと、その働きを科学的に示すための研究事例やエビデンスが豊富なことによりメタボリックシンドローム対応素材として期待されています。
2008年4月より特定医療健診制度が導入されました。厚生労働省によるメタボリックシンドローム診断基準の発表以降、さまざまな立場から予防・改善の必要性が話題となっています。 ・・・とはいうものの実際には、「予防・改善に取り組む気にならない」「何をしていいのかわからない」という方が多いとも言われます。メタボリックシンドローム予防・改善の方法はたくさんありますが、ここでは「行動変容」にスポットを当てて「脱メタボ」を考えてみました。また、「メタボ」が発病にいたったとき、どうなるのか・・・「メタボリックシンドロームの何が本当に怖いのか」を取り上げ、メタボリックシンドロームの警告に込められた真意と現実についても考えてみました。
メタボリックシンドロームに「勝つ方法」を科学する
「おなかポッコリ」というだけで「メタボ」と呼ばれるほどにメジャーになった「腹囲85cm」。けれども、メタボリックシンドロームは腹囲85cmのことだけをいうのではありません。腹囲に加えて血糖値・コレステロール値や血圧などその他2項目の数値の異常が診断基準となります。数値が異常を示すそれぞれの項目を「イエローカード」に例えると、イエローカードが3枚そろってはじめて「メタボリックシンドローム該当者」となるということです。
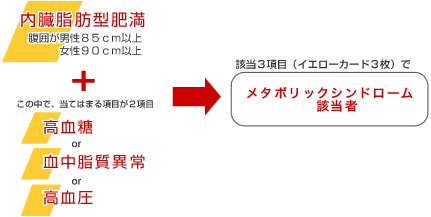
しかし、意外と知られていませんが、
イエローカードを1枚でも減らすことができれば発病に至るリスクは激減する
ということも重要なポイントです。
「勝てない人のパターン」に学ぶ
心理学の用語で「行動変容」という言葉があります。「行動変容」とは、習慣化された行動パターンを変えることを意味します。メタボリックシンドロームは、食生活や運動などの生活習慣をいい方向に変えること、すなわち「行動変容」なくしては予防・改善ができないと言われます。そこで、「行動変容」を軸に、「勝てない人」のタイプを考えてみました。
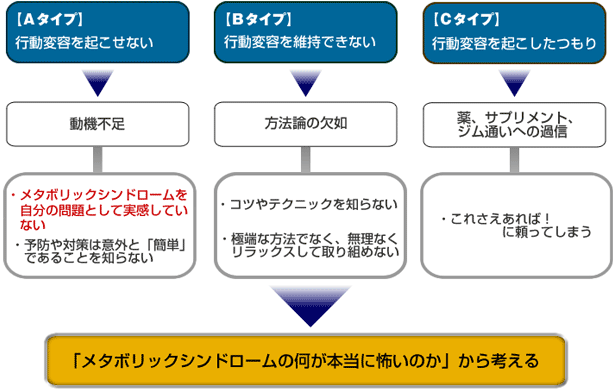
「メタボ」の警告に込められた真意と現実
誰かに「おむつ」をはかせてもらう自分(!)を
想像してみてください
ところで、メタボリックシンドロームの警告に込められた真意とは何でしょうか?
メタボリックシンドロームが進行すると、心筋梗塞や脳卒中になる危険性が非常に高くなると言われています。医療技術の進歩により寿命が延びた一方で、発病後「要介護(寝たきり)」の高齢者が増加する・・・ということが予想されています。これがまさしくメタボリックシンドロームの警告なのです。つまり・・・「要介護(寝たきり)」になるとは・・・
「おむつ」をはき、誰かにその世話をしてもらう状態に他なりません。
寝たきりになるということは、本人の心理的苦痛だけでなく、家族全体の生活にも影響を及ぼします。そういう意味ではメタボリックシンドロームは高齢者だけの問題ではなく、介護にあたる若・中年世代を含む家族全員、ひいては社会全体のQOLの低下につながるのです。私たちが今後、長寿社会の中で暮らす以上「メタボ」は他人事ではありません。
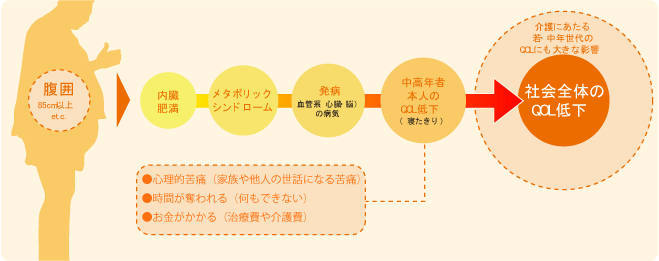
しかし、メタボによる「寝たきり」を回避するのは実は難しいことではありません。
メタボリックシンドロームという状態は「病気のぎりぎり一歩手前」の状態を指します。発病してしまうともはや手遅れですが、下の図のとおり発病までのプロセスは非常に明快です。
がんや花粉症のように発症の原因や進行の道筋が特定できず治療法も複雑な疾病に比べると、その主な原因は「内臓脂肪」であることが特定されており、進行の逆をたどることで確実に予防・改善が可能であると考えられます。
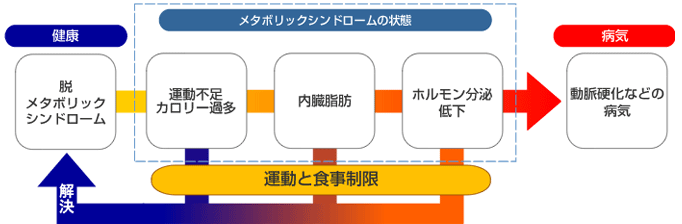
先に述べたとおり、「行動変容」により上の図の矢印の逆をたどり、診断基準項目の中の「イエローカード」を1枚減らすだけで発病のリスクは激減するのです。
「脂肪の持ちすぎ状態」をストップ!縁の下の力持ち「L-カルニチン」がサポート
そもそもメタボリックシンドロームは「脂肪の持ちすぎ状態」だと言えます。L-カルニチンは「脂肪燃焼をサポートする」栄養素であるという基本機能を持っていることから、メタボリックシンドロームの診断基準であるイエローカードのどのケースにも深くかかわっています。
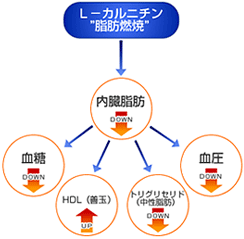
メタボリックシンドローム診断項目の数値の変化
メタボリックシンドロームとL-カルニチンとの関わりを示す研究事例をご紹介します。

84人の健康な高齢者にL-カルニチンを1日2回2gずつ、4週間摂取してもらったところ、「体脂肪」「総コレステロール」「LDL(悪玉コレステロール)」「トリグリセリド(中性脂肪)」のすべての数値が低下、「HDL(善玉コレステロール)」の数値が上昇するという結果が報告され ています※2。
このうち、「トリグリセリド」「HDL」はメタボリックシンドローム�の診断基準に該当する項目であり、脂質代謝に関わるL-カルニチンの摂取はメタボリックシンドロームの予防・改善に役立つことが期待されています。すなわち、イエローカードのいずれか1枚を減らすために、「縁の下の力持ち」として活躍するわけです。
ただし・・・、これには前提があります。つまり、
第一に「行動変容」があり、その次に「Supplement=補うもの」として脂肪燃焼をサポートする
L-カルニチンがイエローカード返上を支援するサポート役として活躍します。
「L-カルニチンがあなたの『メタボ習慣』に負けるとき」というこのページのタイトルに私たちのメッセージを込めてみました。
つまり・・・L-カルニチンを摂れば脂肪燃焼が促進されるのは事実ですが※2、行動変容なくしてはL-カルニチンの活躍も帳消しになってしまうということです。
L-カルニチンと「行動変容」を組み合わせて体重減少

27歳~64歳の肥満傾向にある100人を同数の2つのグループに分け、一方のグループにL-カルニチンを1日3回1gずつ、もう一方にプラセボを摂取してもらい、カロリー制限を加えた上で4週間後の体重の変化を調べたケースです。
結果として、L-カルニチンを摂取したグループの方が体重が顕著に低下しま�した※3。同時に、「行動変容」にともなうプラセボ群の成果にも注目すべきものがあります。
※プラセボとは偽のサプリメントでL-カルニチンを含まないものです。なお、被験者にはそのことはわからないようになっています。
「行動変容」を起こすためのきっかけ
メタボリックシンドロームに陥る傾向にある人の生活習慣はエネルギーの持ちすぎということでは共通しています。したがってそれを予防・改善するためには、食と運動についての「行動変容」を起こせばいいのです。メタボ予防の方法はさまざま紹介されていますので、ここでは心理面から「行動変容」のためのきっかけになるかもしれないいくつかのポイントをまとめてみました。
● 誰かに「おむつ」をはかせてもらう自分を想像してみてください
● 月に1~2回、同じ日に3~5回体重を計って記録する日を作ってみてください
体重は意外なくらい目まぐるしく変化するものです。体重の増減に一喜一憂することなく冷静にウェイトマネジメントができます。
●「神経質にならずに、本気になること」が大切です
●「運動しないライフスタイル」は転職や異動、転居や退職などの人生/ライフスタイルの転機とともに訪れます
米マクマスター大学の運動生理学者スチーブン・ブレイ氏によると、大学に入学した時点で運動習慣を手放す人がもっとも多いそうです(出典:TIME/US版2008年3月号)。新しい仕事に就く、結婚する(結婚前後で体型が変わることが多い)、などの変化もすべて「運動しないライフスタイル」につながりやすいので注意が必要です。これらはいわば「マイナスの行動変容」といえます。
● 食べたものの記録を取って、自分がいかに「太る努力」をつづけているかを発見してください
「いつまでもデブと思うなよ」の著者岡田斗司夫さんが実践して15ヵ月で50kgの減量に成功された「レコーディングダイエット」によれば、我慢や後悔は禁物とのこと。記録するといかに自分が太り続ける努力を続けて来たか、本当にほしいもの以外の物を食べていたかが分かる・・・そうです。
メンタル面での「本物の変化」が起こせれば、行動変容を起こしたり、変容後の習慣を持ち続けることはもはや困難ではありません。脱メタボは一時の目標ではなく、「一生もの」として持ち続けなければ意味がありません。